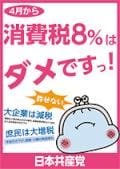25年度の10月の柏原市議会でも、「学力を向上させるためにも学校別の平均点を公表すべきである」と要望する議員もいましたが、私は公表すべきであるとは思いません。
赤旗の新聞記事は、「子供に豊かな学力を保障するには、競争させるのではなく、教員の数を増やし、1クラスの人数を減らして、1人ひとりに目が届くようにすること、そして、教員が自主的な研修に参加できるようにすることこそ必要です。」と書かれています。
(新聞記事をクリックしてください)

私が24年度6月議会で個人質問をした内容を議事録から紹介します。
小学校3年生以降の少人数学級の実施のお考えについてお聞きしましたが、柏原市独自では考えていないという悲しい答弁でした。
日本共産党は、引き続き国の政治の責任として、国政で党国会議員団を中心に実現に向けて頑張ってまいります。
また、答弁で習熟度別指導をしているということでしたけれども、習熟度別はいろんなやり方があると思いますけれども、世界的にはこのやり方は破綻している。科学的に見ても、全部の子どもの学力を上げるには、多分、私はなっていないと思うんです。この問題は、また一回じっくりと時間をとってやりたいと思います。
冒頭でも述べましたが、教育関係の条例は、教育への徹底した競争原理を導入するものです。手始めに公立高校学区撤廃と統廃合、小・中学校選択がねらわれています。もともと日本は、国連、子どもの権利委員会から、高度に競争的な教育制度のストレスなどが子どもの発達をゆがめていると、繰り返し是正の勧告を受けてきました。
また、大阪府がつくった教育関係の条例ですけれども、条例は教職員を支配し、統制し、首長への絶対服従を迫るものです。競争教育を進めるために、条例は教職員を処分の乱用で脅かし、首長の言いなりにさせようとしています。その象徴は、同じ命令に3回違反した先生は首にするという前代未聞の条項です。橋下徹氏は、公務員だから命令に従うのは当たり前と言いますが、教育は命令、服従で行うものではありません。
教員は、目の前の子どもたちに接しながら、自分の判断で教育を行う教育の専門家です。それでこそ、子どもと保護者に責任を負うこともできます。こうした教育の条理に反して、首をちらつかせ、命令を聞かせていけば、生き生きとした教育は影を潜めます。被害者は、人間味を失った先生に教わる子どもたちです。
多分、部長さんは見てはれへんと思うんですけれども、2月16日、17日に、毎日放送の夕方の「VOICE」という番組で、まだそのとき、大阪維新の会がこの条例を上げるとか、よくテレビに中西教育長も映っていたあのときですけれども、大阪維新の会が進めていた教育基本条例に警鐘を鳴らす特集が組まれました。「アメリカ流教育改革の落とし穴」「ニューヨーク教育現場のひずみ」と題した番組でした。アメリカでは10年前に「落ちこぼれゼロ法」という法律が施行されました。全米学力テストが義務化され、テスト結果を自治体ごと、学校ごとに公表し、結果を出さない先生、平均を出されて平均点の悪い学校の先生を首にするという内容のものでした。学校現場で行われたことは、平均点を上げるために、勉強がしんどい子を前日に先生が避けて、あしたは休んでいいよとか、先生がそのテスト中にぐるぐる回って答えをどんどん教えていく。そんなことも起こってしまって、10年たった今、その「落ちこぼれゼロ法」をつくった教育の専門家が、結局、法律は失敗やった、テスト結果を重視しただけで、教育の質は上がるどころか下がってしまったと振り返り、大阪の教育基本条例にも多くの共通点があることを指摘しています。
アメリカでも、維新の会でも手本とされたのが、イギリスでのサッチャー首相が取り組んだ教育だったということが明らかになっています。
ここで、教育長にお聞きしたいんですけれども、やっぱり今、一人一人が主人公になる、本当に子どもにとっていい教育を保障しようという形で、今、市教委も一生懸命いろんな方法を考えられていると思うんですけれども、私も今るる述べさせていただきましたが、教育長個人として、大阪府のあの条例、すべての子どもの学力が保障されると思われるでしょうか、お尋ねします。
稲田邦敏教育長 あの基本条例は、もともと昨年の9月ぐらいに維新の会が提案してきたわけですけれども、そのときは教育基本条例につきまして1本でございました。
いろいろ、先ほど、中西教育長の話とか、教育委員さんとそれから維新の会の折衝とか、それからまた大阪府の教委の幹部とのとか、それから公立学校の校長とか、いろいろやってきた中で、提案してきた中身が、初め、私たちの衛星都市の教育長の中でも、これはちょっとやり過ぎではないかということで、一定反対をしていきたいということで意思統一してきたわけでございます。
そのいろいろなやりとりの中で、最終的に教育基本条例につきましては、府立学校条例と、それから教育行政基本条例ですか、この2本立てになったわけでございます。
これについてもかなりお互いに話し合いをして、結果的にこれになったわけでございますけれども、府立学校条例については直接、市町村のほうは関係ございませんので、もう一つのほうの教育行政基本条例、これについてもほとんど10条ぐらいまでしかありませんので、直接、今現在、小・中学校について影響があるかというと、ほとんどございません。
ただ、この運用につきましては、これからまた検討していかなければならないということで今終わっているわけですけれども、今おっしゃいました学校の競争、これにつきましては、一般的に競争という原理は、学校の競争ではなくて一般的なことですと、競争の原理というのは、やっぱり切磋琢磨してやる気が出て、これはいろんな面で効果があると思います。
例えば、子どもたちが運動会で、今度はあの子には100メートル競争に勝ったるぞとそういうふうな気持ちがあれば、そうすればやっぱり練習もするでしょうし、そしてまた運動クラブで、あそこのチームに勝とう、あそこの学校のチームとやったら勝とうとか、これはやっぱり競争心があるから、これはまた伸びていくんであって、これは私はすばらしいことやと思います。
ところが、今、議員がおっしゃいました、学校の競争となりますと、やっぱりやることによって学校の序列化がなされます。そうするとどうしても、例えば小学校10校ありますけれども、1番から10番までつきますけれども、10番のところに行っている学校の子どもたちは、何や、うちの学校は一番べったなんかと、こんな学校に行っているのは嫌やとか、そういうふうに劣等感を持つ子どももあるかもしれません。保護者もしかりかもしれません。
そういった意味では、この学校を要するに競争させるというのは、やっぱりちょっとこれはぐあいが悪いのかなというふうに思います。
柏原市では、そういうことではなくて、平成20年に策定しました「はぐくみ憲章」がございます。この基本理念、目指す子ども像ということで、15の春に一筋の意思を持ったひたむきな姿勢を貫く若者の育成と、これを目指して、幼小中一貫教育をやっています。ですから、これはもう部長が先ほどから何遍も答弁していますけれども、やっぱりこれを進めていくことが、柏原の子どもたちの学力の育成につながるんではないかなというふうに思います。
ですから、これについてはちょっとなじまないかなというふうに思います。 以上です。
橋本 私、心配しているのは、6月大阪府の統一テストをして、今回その結果、学校ごとの平均点を各家庭に返していく。それが9月ぐらいに出てしまうという中では、保護者がすごい連絡網を持っている中では、各学校の序列が絶対されると思うんです、小学校でも中学校でも。そこは本当に慎重に、私も見ていきたいし、心配しているところです。
やっぱり私は、少人数学級、なかなかしんどいというお話やったけれども、私が住んでいますのは堅下北中学校の校区です。堅下北小学校の前ですけれども、例えば、堅下北小学校で言ったら、3年生は40人なんです。今、40人だから1クラスなんです。35人学級になったら20人20人の2クラスになるんです。
堅下小学校、今、3年生は、支援学級の子が入って81人です。だから40人と41人の2クラスで今、やっています。もし35人学級になったら、27人の3クラスになるんです。1人の先生が少ない人数の生徒と一緒になってできるという意味も込めて、やっぱり少人数学級。
奈良市は、小中一貫と一緒に同時並行で少人数学級もやっているという中では、ぜひとも、またなかなか今では難しいけれども、私はやっぱり必要だと思います。
2013年11月11日 7:20 AM |
カテゴリー:しんぶん赤旗, 活動報告, 要望 |
コメント(0)
本日31日、10月議会も閉会しました。その後、中野市長に2014年度予算要望書を提出しました。
2013年10月31日
柏 原 市 長
中 野 隆 司 様
日本共産党柏原市会議員団
幹事長 橋本 満夫
山本 真見
市民要望実現のための
2014年度の予算についての要望書
2014年度予算要望書の提出にあたって
日頃からの市政運営に対するご尽力に敬意を表します。
東日本大震災と福島原発事故から2年7ヶ月が経過しましたが、被災地の復旧の立ち遅れは深刻です。被災者はいまだに15万人もあり行先きの見通しが立っていません。
この時期に、昨年12月に発足した安倍政権は、来年4月からの消費税を5%から8%に増税する決断をしたと発表しました。国民所得が減少している中、しかも生活必需品をはじめとする諸物価が高騰している中でこの決断は、国民の暮らしを破壊し、景気のさらなる悪化を招くことが危惧されます。しかも、社会保障の大改悪により、年金受給額の毎年引き下げ、各種保険料の大幅な引き上げなど、ますます生活や生業を破壊するような動きになっています。
一方大企業は、リストラや人員削減をすすめ、生産拠点を海外に移すことによって莫大な利益を蓄積、270兆円におよぶ内部留保をため込んでいます。これを日本経済に還流させ、国民の所得を増やし、家計を温め、日本経済を内需主導の健全な発展軌道に乗せることこそ政治の責任です。
市政においては、市民の暮らし・生活が大変な状況の中で、地方自治の本旨である「住民の福祉の増進」実現を目指し、市民生活を守るため、国に制度の改善を求めるとともに、来年度予算は、福祉と健康・暮らしなど市民の暮らしを守ることを最優先に取り組んでいただき、市民の皆さんの切実な要求実現に積極的に応えていただくよう要望いたします。
① 健康で長生きできるまち、市民が希望をもって暮らせるための、くらし・福祉・保健・医療制度の充実を(第4次柏原市総合計画 政策目標 1)
1. 介護保険については、国の3原則にしばられることなく、市独自で低所得者への介護保険料・利用料の軽減をはかられたい。また、減免制度の拡充をはかられたい。
2. 介護サービス基盤の整備を引き続き強化し、介護サービスを拡充されたい。
3.「後期高齢者医療制度」は、高齢者を世代別に振り分け、医療の差別化を図るものであり、国に対して、直ちに「後期高齢者医療制度」の廃止を求めるとともに、同制度加入者の低所得者には柏原市独自の助成制度を確立されたい。
4. 高齢者向けケア付き住宅の建設や民間住宅借り上げ・家賃補助制度などに より、お年寄りが安心してくらせる環境づくりにとりくまれたい。
5. 高齢者の熱中症対策や見守り活動を強化されたい。
6. 柏原病院を市の基幹病院として、夜間・休日の医療体制を確立し、市民に信頼される医療体制・医療水準の充実をはかられるとともに、市民に情報提供し、意見も聞き市民との協働で公立病院の役割を果たされたい。
7. 地域医療体制の充実につとめ、特に小児科救急診療を、24時間・365日体制での実施にむけ取り組まれたい。
8. 国民健康保険については、国に負担割合の増額を求め、一般会計から保険料を引き下げるための特別な繰り入れを行い、保険料の引き下げを行われたい。
9. 水道料金は値上げしないこと。
10. 市民税、固定資産税、国保料などの減免枠を住民の生活実態にあわせて拡大されたい。
11. 下水道使用料の減免制度を拡充するとともに、上水道料金の減免制度を導入されたい。
12. 公共下水道使用料は値上げしないこと。
13. 乳がん・子宮がん検診の実施を年1回に拡充されたい。
14. 引き続き妊婦健診の費用の公費負担をより拡充させ、妊産婦全員の妊娠・出産費用の無料化を進められたい。
15. 女性への暴力や性犯罪、DVなど被害をなくす取り組みを強められたい。
16. 女性センターの講座・教室は、働く女性も参加できる時間帯の開催を増やされたい。
17. 生活保護基準の一級地への引き上げと「医療券」の現制度を医療証制度へ切り替えることと、受給期間の制限や医療費負担など、生活保護法を改定しないように国に強く働きかけられたい。
18. 障がい児・者の実態とニーズを把握し、「柏原市第3期障害者福祉計画」に基づいて、安心して福祉サービスが利用できるように、施設整備(グループホーム・ケアホームなど)や施策の充実をはかられるとともに、障がい者施設へ独自での運営費補助制度を創設されたい。
19. 産業会館(KIホール)に公民館をつくり、さらに住民票等の発行できる窓口を設置されたい。
20. AED(自動体外式除細動器)をすべての公共施設等への設置を進められ、日常の点検をはじめ、使用方法などの周知徹底を図られたい。
21. 低所得者や新婚世帯への民間賃貸住宅の家賃補助制度を新設されたい。
22. 高齢者が外出する機会を増やすことは介護予防の観点からも経済効果の観点からも重要であるため、市内循環バスを堅上地域には、土・日曜日も運行されるなど、引き続き市内循環バスの拡充をされたい。
23.高齢者の肺炎球菌ワクチン接種を無料化にされたい。
24.低所得者へのクーラー設置費、電気代への補助をされたい。
25. 要介護者認定者全員に「障がい者控除対象者認定書」を発行されたい。
26. 国民健康保険一部負担金の減免制度を拡充されたい。
② “市民の懐(ふところ)を豊かに”する、雇用問題の解決、産業振興・地域経済活性化をはかる施策の拡充を(政策目標2)
1.市内事業所・小売店の実態を調査し把握に努め、商工業振興、地域経済活性化につながる具体策を講じられ、「中小企業振興条例」をつくられたい。 また、地元業者・住民・専門家を加えた「地域経済再生戦略会議」(仮称)を設置し、中小業者の要求、地域の要求を敏速に、正確に施策に反映できる仕組みをつくられたい。
2.不況の中での中小企業対策として、市独自で緊急借り入れの「中小企業緊急融資制度」を新設されたい。また、廃止された中小企業利子補給金制度を復活されたい。
3.柏原市が契約する工事や委託業務で働くすべての労働者に対して、本市が定めた最低賃金基準を盛り込んだ、「公契約条例」を制定されたい。
4.柏原市地域就労支援センターの人的配置も含め、雇用促進のためのきめ細やかな対応を引き続きすすめられたい。
5.柏原市の商工業対策を強化するため、市としての担当者を増やすなど、 体制強化をはかられたい。
6.商店街活性化のため、抜本的な「商業振興計画(仮称)」を立て、取り組みを強化されたい。
7.住宅などを改修するとき、地元業者に工事を発注した場合、自治体が費用の一部を負担する住宅リフオーム助成制度を新設されたい。
8.農業基盤整備や後継者育成に努め、農業振興をはかられたい。
9.有害鳥獣駆除対策事業の拡充をはかられたい。
10.農業をはじめ国内産業に打撃を与えるTPP(環太平洋連携協定)参加 に柏原市として反対を表明されたい。
11.労働者の相談窓口を設置されたい。
③ 子育て世代が、柏原で“安心して生み、子育てできる”未来ある子どもたちへの支援の拡充のために(政策目標1)
1.柏原市の子ども医療費助成制度の対象を通院でも中学校卒業までにひろげ、大阪府の制度拡充および、国の制度化をはたらきかけられたい。
2.市立柏原病院での病児・病後児保育の実施をされたい。
3.法定化された細菌性髄膜炎ワクチン(ヒブワクチン)・肺炎球菌ワクチン接種に対して引き続き公費助成をされ、個別通知などにより接種を勧奨されたい。
4.ポリオ不活化ワクチン接種に対しては、引き続き公費助成をされたい。
④自然環境をいかし、生活環境を守り、安心して住み続けられる、まちづくりのために(政策目標2・3)
1.山間地などの乱開発を許さず、市民の憩いの場としての緑と景観など環境を 守られたい。
2.「水資源保護条例」をつくり、住民の貴重な共有財産である地下水を守り、自己水の供給を確保されたい。
3.恩智川の浄化対策をすすめ、水辺環境の改善をすすめられたい。
4.了意川周辺の環境整備事業として、街並みを活かしたまちづくりにとり くまれたい。
5.市民がいつでも、憩える、公園、広場を増設し、植栽、日陰、ベンチ、 トイレ、水道の設置をすすめられたい。
6.一般家庭ごみの収集は、無料化を堅持されたい。
7.民間企業の井戸の実態、地下水のくみ上げ等について、市独自で実態調査を実施されたい。
8.「環境保全条例」を作成し、快適な環境づくりに努められ、そして、緑化の促進を図られたい。
9.大和川の支流である、原川の水質浄化については、奈良県の流域自治体と 連携してすすめられたい。そして、ホタルの飛び交う原川を取り戻す取り組みをすすめられたい。
10.自然環境を整えるため、市民に対しての太陽光発電設置助成制度を拡充させ、公共施設に計画的に太陽光発電などを設置し、公共施設や公用車など地球温暖化対策を率先して実施されたい。
11.竜田古道の里山公園については、公園用地の柏原市への譲渡を撤回し、今 後において、環境事業組合で維持管理費を支出されるようにし、市民が憩える公園として運営されたい。
12.自然環境を整えるため、市民に対しての太陽光発電設置助成制度を拡充させ、公共施設に計画的に太陽光発電などを設置し、公共施設や公用車など地球温暖化対策を率先して実施されたい。
《歩行者対策など、バリアフリーで安全・安心して歩けるまちづくり》
1.国豊橋北側から高井田駅までの、歩道拡幅整備を早急にすすめられたい。
2.旧170号線の歩道未整備箇所に歩道を早急に設置されたい。
3.府道大和高田線及び府道本堂高井田線での歩道未整備区間の整備をすすめ、歩行者安全対策をはかられたい。
4.市道石川東線の水道局以北の歩道整備をすすめ、安全対策を進められたい。
5.「温水プール」までのアクセスに歩道を設置し、利用者の交通安全対策を はかられたい。
6.本格的(幅3m以上)な歩道や自転車道設置など、高齢者・子どもや障がい者の方が車椅子でも自由に往来できるように改善をされたい。
《災害に強いまちづくり》
1.「防災計画」の見直しにあたっては、市民の命と財産を真に保護できる「計画」とすること。国の「防災基本計画」に見られる従来型の「応急対策中心」ではなく、「災害の未然防止対策」を中心に据えた柏原市独自の「防災計画」を策定されたい。
2.すべての市民が「自分の身は自分で守る」という防災意識を持つことは、防災対策の基本である。「自己責任論」の立場から、行政の責任を後退させてはならない。防災意識の啓発、訓練を「計画」の中で最優先に位置付け、行政の責任でされたい。
3.災害弱者と言われる高齢者、障がい者等への応急対応策の「計画」を、きめ細かく、心の通ったものとして策定されたい。
4.住宅に対しての耐震診断・耐震改修に対しての予算を大幅に拡充されたい。
5.老朽化の公共施設については、順次計画的に補強・建てかえを行われたい。
6.市で急斜地の地すべり防災対策を講じられたい。
7.生津川の改修を引き続きおこなわれたい。
⑤子どもの健やかな成長を保障するための教育環境の整備と充実、歴史・文化遺産を守り、活気ある文化・スポーツの発展のために(政策目標4)
1.文部科学省は2017年度までに公立小中学校の全学年に35人以下学級を実現したい考えを示したが、国の実施を待つことなく、市独自で教員を配置し、大阪府の実施制度の拡充を要望し、小学校3年生以上での実施をされたい。
2.小中一貫教育は人的配置を充分に行い、現場の教師や生徒・児童の声を反映させ、他市の状況も参考にされ慎重に行われたい。
3.放課後児童会の施設整備に努め、放課後児童会の受け入れは、4年生までに拡大、さらに6年生まで目指されたい。
4.耐震化工事を急ぐとともに、トイレの改修など教育環境の整備につとめられたい。
5.学校の天井や照明器具などの非構造部の耐震性について、教育委員会が責任を持って詳細検査を行なわれたい。
6.小中学校のすべての教室に早急にクーラーを設置されたい。
7.就学援助制度は教育を受ける児童・生徒の権利であり、基準の引き上げと給付改善をおこなわれたい。
8.引き続き学校安全監視員を配置されたい。
9.中学校給食実施に対しては、現在小学校で提供している「安心・安全・おいしい給食」の質・量を落とすことのないように中学校でも提供するために、充分な人的確保が出来る予算措置をされたい。
10.幼稚園教育に対しては、児童数の減少などを理由に一律に休園や廃園するのではなく、3年保育や教室へのクーラー設置・給食実施等の教育環境を充実されたい。
11.学校序列化につながる全国及び大阪府統一学力テストの学校別平均点の公表はやめ、府の統一テストは受けないようにされたい。
12.学校図書室を充実し、専任の図書司書の配置など抜本的に強化されたい。
13.柏原図書館の充実、市の図書資料費を大幅に増額され、質の高い図書館行政をすすめられたい。
⑥ 財源の確保、効率的で民主的な行財政の確立と市民参加の市政へ(政策目標5)
1.市の安定的な財源の確保のうえからも、産業振興・地域経済の活性化対策への抜本的な拡充と柏原市の特色を生かして、若い人たちが住み続けたくなるような魅力のある柏原、また、少子化対策の強化で安心して生み、子育てし、暮らせる柏原など、長期展望に立った施策の拡充をされたい。
2.入札制度においては、公平性・透明性・競争性が高い制度を確立されたい。
3.市政運営するにおいては、市民が納得のいく歳出に心がけ、清潔・公正な開かれた市政を目指されたい。
4.柏原市の職員は、憲法15条に謳われている「すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者でない」という理念に基づいて業務が行えるように徹底されたい。
5.自衛隊での新人職員研修及び職員研修は行わないこと。
⑦憲法を守り、非核・平和の柏原市を築くために(政策目標5)
1.平和・民主の憲法と地方自治の精神を尊重した市政をすすめられたい。
2.「平和都市宣言」の具体的な計画と活動のための予算を強化し、核廃絶・ 平和のためのとりくみを強められたい。
以上
2013年10月31日 9:29 PM |
カテゴリー:活動報告, 要望 |
コメント(0)